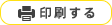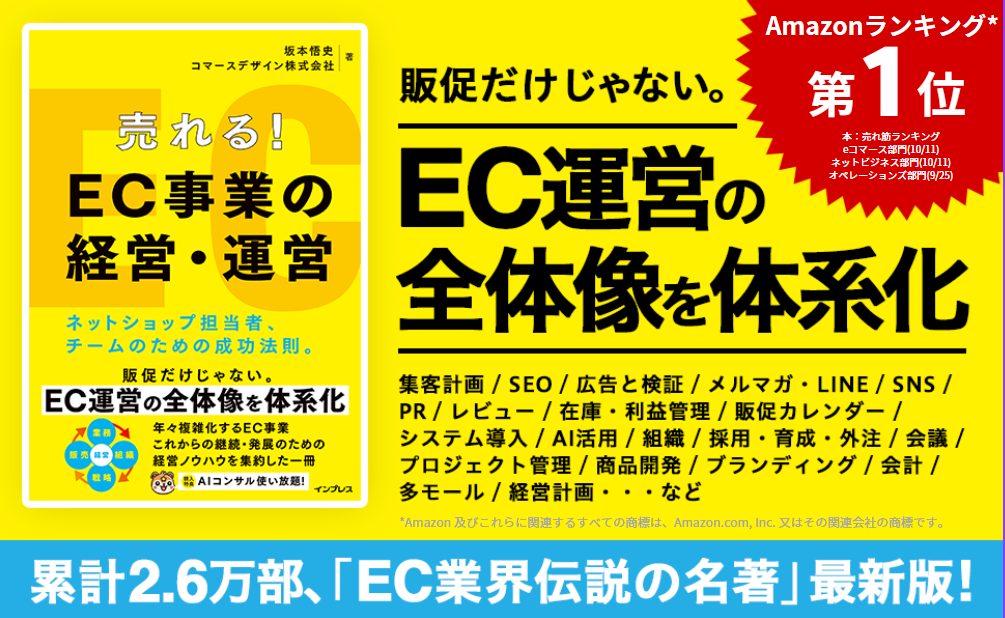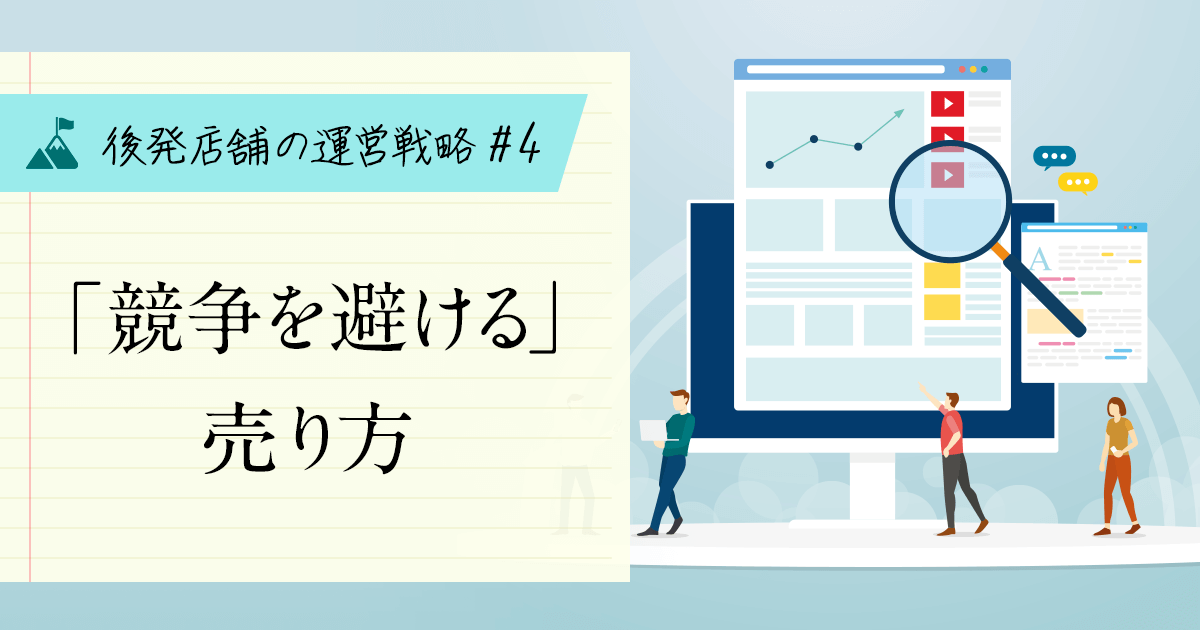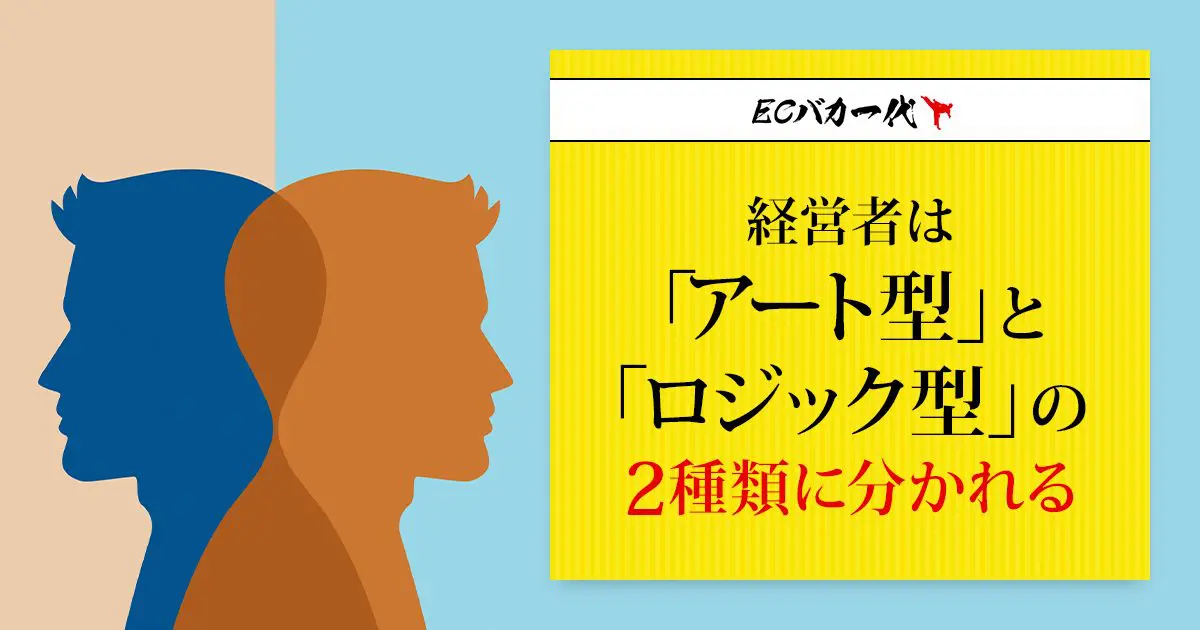
こんにちは、坂本です。
今回は、「アート型経営者」と「ロジック型経営者」の違いについて話をします。
私の仕事柄、多くの経営者の方と接してきて、日頃から感じていたことをまとめてみました。人をそんなに安易に2つのタイプに分けちゃいけないと思いますが、あくまでも、私が感じている傾向でざっくり分けてみたという感じです。自分はこっちだなとか、うちの社長はこっちのタイプだななど、割とどちらかに分類できたりするなと。経営に正解はありませんから、「これが正しい」というのではなく、双方の考え方や重視する点をお互い知り合うのが大事ではないかと思うわけです。
ご自身や会社のことを、少し引いた視点で見つめ直したり、違う角度から捉えてみたりする、そんなきっかけになれば嬉しいです。
- 目次 -
経営者は大きく「アート型」と「ロジック型」に分けられる
経営者には、大きく分けて「アート型」と「ロジック型」の2つのタイプがいます。私が作った分類です。
ざっくりとした概要は以下のとおりです。(詳しくは後述します)
- アート型
- 感性が光る商品を扱う
- 経営もアーティスティックで、直感を頼りに事業を育む
- チャンスも課題も、感覚から生まれることが多い
- ロジック型
- 合理的な商品を合理的に取り扱う
- 地に足のついた経営を好み、戦略を論理的に説明する
- 筋道立てて課題を解決し、成長を重ねることに面白さを感じる
- ときどき理屈の限界を感じることもある
これらのタイプは、本人の性格だけでなく、扱っている商品の特性やこれまでの人生経験など、さまざまな要素が掛け合わさって形づくられます。
もちろん、100人いれば100通りのやり方があるのが経営なので、誰もがどちらかのタイプにきれいに当てはまるわけではないんですけど、私から見て、あきらかに掛け合わせによる「型」があるなと思ったのでお話します。この2つの型は、世界の見え方なども、そもそもだいぶ違っているような気がします。あえて両極端な「型」とすることで、わかりやすく考えられるのではないかということです。アート型の人には、アート型の。ロジック型の人にはロジック型の、それぞれの正解と経営課題があるように思います。
では、ここからそれぞれのタイプの特徴や、直面しやすい課題と対処法を見ていきます。
アート型の特徴は「独自の世界観」

アート型の強みは「他と比較できない魅力」
アート型の経営者は、直感を大切にしながら、お店やブランドをつくり上げていきます。
感覚を重視するため、数字や言葉で型にはめるような表現や、分類されることをあまり好まず、安易に言語化しません。我々コンサルタントが「品質・価格・利便性のどれを重視していますか?」と尋ねると「どれでもあるし、どれでもない」といった答えが返ってくるようなタイプです。
でも、そんな独特な感覚から生み出される「他と比較しづらい魅力」を武器にできるのがアート型の強み。こういう独自の感覚は、簡単に表現したりカテゴライズしたりできないので、模倣されにくいんです。
たとえば、ラーメン店を想像いただくとわかりやすいかもしれません。塩や醤油といった味のくくりではおさまらない「空間作りまで含めての一杯」みたいなお店ってたまにありますよね。器やテーブル、照明なんかも含めてトータルで「雰囲気のある」「ちょうどよさ」を感じる、あれこそがアート型の魅力です。(この言語化の難しさがアートの何たるかですよね、まさしく)
ECでいうと、特にアパレル業界に多い気がします。
そもそも、ファッションって感覚で判断するものですよね。「センス」がものをいう。
アパレル商品は、検索キーワードだけでは探しきれないニュアンスがありますよね。お客さんも「こういう感じ」みたいな商品の探し方をしますし。だから、自分の思っているセンスやイメージに近いお店を覚えておきたいので、ほかの商品群に比べ、ブランド指名検索されたり、トップページを直接ブックマークしてもらえたりする。
つまり、アート型は、大成すると他のブランドがどうとかに左右されることなく、お客さんが自ら見に来てくれるようになるわけです。強い引力を持つわけです。
アート型の悩みは「世界観をスタッフに伝えきれない」こと
ただ、アート型の経営者は、こうした独自の世界観があるがゆえに、現場にその感覚を理解してもらうのに苦労します。
本人の頭の中では独特なイメージがあるので、安易に言語化したくない。なぜなら、「じゃあ、塩味で」というと、現場のメンバーは、塩味を作り始めるんですが、経営者本人からすると、「その塩味は、塩味だけど違う」と思っているため、「塩味」と言いたくない、言えない…みたいな独特な葛藤があり、自分の世界観をスタッフにうまく伝えられないんです。
本人はその複雑な世界をそのまま理解できますが、他の人も同じように理解して再現できるかというと、それは難しいんですよね。
なので、アート型なのに頑張ってイメージを言葉で説明するんですけど。でも言葉にすると、どんどんあの絶妙な塩加減から離れていく気がしてくる。それで結局、人に任せられず「この塩加減は俺にしか出せない」と経営者自身がずっとすべての商品やブランドをディレクションし続けてしまう・・こんなことがよくあります。
もちろん、ディレクションすること自体は間違いではないんです。でも規模が大きくなってくると負荷も大きくなりますよね。そうなれば当然、経営者がボトルネック化して、仕事が滞留するという問題が頻発します。
こうなると、エネルギーが肝心なお客さんに届かなくなってしまい、成長を鈍化させてしまうんですね。
アーティスティックなことができる稀有な才能をもつ経営者は、他の人にはできない世界観を作る仕事に集中するべきなんですが、この集中する環境作りが難しいんです。
「業務の委託方法」と「苦手を補う相方」がカギ
では、アート型の経営者は、どのように独自の世界観をスタッフに共有して任せ、ボトルネック化を避ければいいのか。
ポイントになるのが「業務の委託方法」と「苦手を補う相方」の2つです。
対策1:定型業務から委託する
まず1つ目は、仕事を細かく分解して、定型的な業務から委託できないかを検討することです。
仕事を分解してみると「アート」だと思っていた仕事の中にも、実は単純作業が含まれていた・・なんてことがよくあります。なので、そこから切り出すと、ボトルネック化を解消できますよ、という話です。
アート型の方が頭の中に描く世界観は、本人が思う以上に複雑なもの。そのまま誰かに共有するのは難しいので、いきなりすべて渡すのではなく、業務を細かく分解して「再現性のある定型的な業務から委託」するのが現実的。
具体的には、ブランドのディレクションとかバイイングといった中核業務の前に、問い合わせ対応やSEOなど比較的定型化しやすい業務から任せていくイメージです。
ちなみに、当社ではこれを「委託と委任」と呼んでいまして、まずは「委託」から始めて、だんだんと「委任」へとレベルを上げることをおすすめしています。
簡単に説明すると、以下のとおりです。
- 委託
- 比較的ルール化・標準化された業務を外部や他のメンバーにお願いすること
- 例:受注処理や在庫管理、出荷作業など
- 委任
- より責任や判断を伴う業務をまるごと任せること
- 例:予算管理を含めた仕入れなど
定型業務の「委託」を通じて、アートな感性を伝承していくと、だんだんと中核に近い仕事も渡せるようになっていきます。つまり、委任できるようになります。
そうすると、たとえば、商品ページ作成とか、SNS・広告運用といったアート型の感性が必要な領域も、一緒にやりながら伝承していけるようになります。
このあたり詳しくは、拙著で詳しく紹介しているので、ぜひお読みください。
対策2:足りないところを補ってくれる「相方」を見つける
もう1つの対策は、アート型の経営者が作った世界観を一緒に形にしてくれる「相方」のような存在を見つけることです。
ここで言う相方は、単なる右腕やナンバー2ではなく、お互いの欠点を補い合える「半身」のようなパートナーを指します。例えるなら、ジブリの宮崎駿さんにとっての鈴木敏夫さん、HONDAの本田宗一郎さんにとっての藤沢武夫さんのような方です。CEOに対するCOOみたいな感じですね。
アート型の経営者が右脳だとすれば、その相方は左脳のような存在です。実務的に世界観を現実へ落とし込む役割を担い、世界観を翻訳できる人だといえます。このあと説明するロジック型の人と言ってもいいかもしれません。スティーブ・ジョブズにとってのティム・クックもそんな感じでしたね。
ではなぜ、アート型の経営者にはこうした相方が必要なのかというと、アート型の持つ独自の世界観を、ビジネスとしてより発展させていくためですね。
アート型の経営者って、本当に豊かな感性で、他の誰も真似できないような世界観を創り出す天才だと思うんです。でも、繰り返しお伝えしているように、どうしても感覚的な部分が多い。だから、その世界観を組織全体に浸透させて、事業として安定的に成長させていくのに苦労します。決して威圧的ではないけれど、そのセンスからある意味独裁的に見えてしまう側面もあります。
そんなときに、相方が世界観をちゃんと理解した上で、それをテキパキと具体的な戦略とか仕組みに落とし込んでくれるわけです。結果、本来の強みである、アーティスティックな仕事に集中できる。理想的だと思いませんか。相方が、その「センス」を大事にし、社内外に上手に伝えてくれれば、憧れ、ファンとして尊敬してくれるようなメンバーが集まってくれるようにもなりますよね。
ロジック型の特徴は「再現性の高さ」

ロジック型の強みは、再現性の高さ
続いてロジック型。
このタイプの経営者は、アート型とは対照的で、感覚よりも根拠で判断したい人が多いのが特徴です。
予測やデータ分析に強く、市場の状況や規模、自社の立ち位置などを数字や言葉でしっかり把握し、先を読みながら「競合はこうだから、うちはこう攻めよう」といった感じで、戦略を組み立てるのが得意です。
アート型のMDは、なかなか再現するのが難しく、メンバーが習得しづらいもの(ロジックがわからないので)ですが、ロジック型のMDは、何よりロジック(考えの筋道)がはっきりしているので、○○な場合はこう、条件分岐としてはこう、判断基準はここを見る、などとメンバーも習得しやすいです。このように、言語化して多くの人に考えを共有することができ、再現性のあるビジネスを構築するのが得意です。なので、マニュアルやテンプレートを整備してメンバーを増やし、ぐるぐる仕事を回して拡大していけるのもこのタイプですね。
とはいえ、必ずしも大きな組織を運営しているとは限りません。なかにはお一人で組み上げた複雑なシステムを駆使して、すべてを完璧にコントロールしている方もいらっしゃいます。本人の方針によって規模の大小は当然異なりますが、やろうと思えば組織化できてしまうんだろうなぁ、と思います。
実際にコンサルティングの現場でも、そのロジックの明快さに「なるほど、勉強になります」と感じながらお話を伺うことが多いです。
ロジック型の悩みは、差別化しにくく、模倣されやすいこと
そんな合理的なロジック型の経営者ですが、実は「差別化がしにくく真似されやすい」という課題を抱えがちです。
どういうことかというと、論理性と合理性が高いということは、属人性が強いアート型と違い、外側からも「どういうビジネス構造になっているのか」が読み解けてしまうんですね。
- こうやって集客して、こうリピートさせてるんだな
- このページは引き込み用で、こっちで稼いでるな
みたいな感じです。
つまり、手の内が読まれやすい。話が伝わらずに苦労するアート型とは正反対の悩みですね。
そのため、成果の出る構造を作り上げても、競合にどんどん模倣されるリスクがあります。
特に大手が入ってきた場合には、美味しいところ取りをされたのちに、資金・体力勝負に引きずりこまれることもありますね。これもなかなか辛い・・。
ブラックオーシャン戦略でニッチを攻める
では、模倣されやすいという弱点を、ロジック型の経営者はどう克服すればいいのか。
あくまで1つの方法ですが、私が考えるのは、ライバルが模倣しにくい、大手があまり参入しないであろうニッチなジャンルに絞り込み、そこで確固たるポジションを築く戦略です。
しかも、ただポジションを取るだけでなく、その領域で大手がやらない面倒な仕事まで対応したり、バックヤードまで磨き込んで徹底的に合理化したりします。
つまり、ニッチな市場に、他社が容易に攻め落とせない「城」を築き、その領域における強者となるのです。
こうすることで、表面的な模倣はされても、自社のポジションをまるっと脅かされるような事態は回避しやすくなります。
ちなみに当社では、これを「ブラックオーシャン戦略」と呼んでいます。詳しくは下記の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
アート型とロジック型、どちらも正解であり、優劣ではない
余談なんですが、そもそもなぜ人によって、こんなにもタイプが違うのか。少し掘り下げてお話してみたいと思います。(このように言語化を試みたくなるのが、ロジック型の性分かもしれません。何を隠そう、私坂本も典型的なロジック型です)
言語学の偉人いわく、人間は、言葉によって世界を認識しているのだそうで。
たとえば、日本語では「蝶(ちょう)」と「蛾(が)」を別物として扱い、なぜか蝶に対して良いイメージを持っていますよね。ところが、フランスではどちらも「papillon(パピヨン)」と呼び、あまり区別をしていません。つまり、蝶も蛾も同じようなものとして見ている。
つまり、人間は言葉によって、無意識のうちにその物事の「見え方」や「捉え方」を認識しているというわけです(ややこしいですね、すいません)。
それで、アート型の人とロジック型の人とでは、この言葉の認識というか扱いが違います。
まずロジック型の人は言語化し、説明することに長けています。「ラーメンを売ろう」という話をすると「目的は?手段は?どの順番で進めよう?」と、体系立てて状況を整理したり理解したりしようとします。
一方で、アート型の人は言葉にすると思っていることと変わっていくので、言葉以外の表現方法(絵や音楽やダンスなどもそうですよね)身体的な表現を駆使して紡いでいくような動き方をします。
「こういう感じでグッとやったら形になりそうよね」と先のことを妄想していたり「別に順番を整理してもいいけど、全部つながってる話だし分けきれないよね」と整理や体系化をあまり重視しなかったりします。
要は何が言いたいかというと、捉え方や強みの違いなだけであって、決してどっちが優れているとかそういうことではないということです。
人は弱みや欠点にすごく敏感なので、こうしてタイプ別の短所を整理すると「克服しなくちゃ」となりがちなんですけど。でも、コンプレックスに思う必要はまったくありません。
アート型の独特な表現とか、ロジック型の明解な分類みたいな「とがった個性」が損なわれる方がもったいないと思います。
人によって世界の捉え方が違うのは当たり前です。その前提に立ったうえで「自分はどういう視点を持っているのか」を理解し、まずそれを活かしましょう。隣の芝生は青いもの。「なんで自分はこうなんだろう」と自分の生まれ持った性質を否定したり、他者と比べて必要以上に悩まないようにしたいものです。
足りない部分は誰かと補い合えばいいんです。たとえば、自分がロジック寄りだとしたら、世界観を大事にするアート型の誰かと組むことでバランスが取れるかもしれません。
苦手を補ってくれる反対タイプの方との出会いを、ぜひ大切にしてください。
特性に合った「ちょうどいい経営」を見つけるために
今回はアート型とロジック型の2つのタイプについて説明してきました。
あなたが経営者ならご自身のこと。または、勤務先の社長のことを想像してみてください。たぶんどちらかの傾向があるんじゃないかなあと思います(もしあてはまらなかったらすいません)。
それぞれ紹介した強みや弱点をもとに、どう経営判断をすればいいのか。あるいは、どう支援したらいいのか。考えてみていただくと、よりスムーズにコミュニケーションが取れると思います。
みなさんの特性にあった「ちょうどいい経営」を見つける参考になれば幸いです。
P.S.
経営に唯一絶対の正解はありません。
自分のタイプを深く理解し、その特性に合わせた組織運営や戦略を選択することが、持続的な成長を達成するうえで大切です。合わないものは合わないし、無理なものは無理だったりしますから。
当社のコンサルティングでは、数字やサイトのページだけを見るのではなく、扱う商品や事業全体、そして経営者ご本人の人柄や人間関係まで含めて、全体を見てその方にあった経営をサポートしています。また、苦手を補う反対タイプの方の採用をお手伝いすることも可能です。
ご興味のある方はぜひ以下のページをご覧ください。ぜひお話しましょう
カテゴリー: EC戦略論