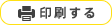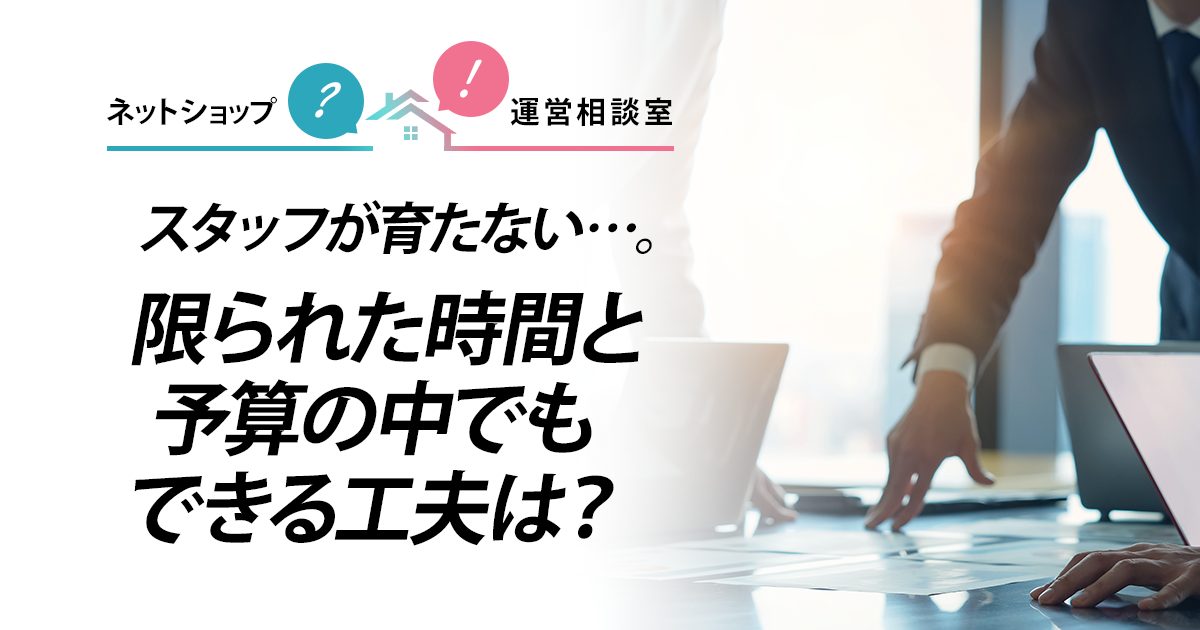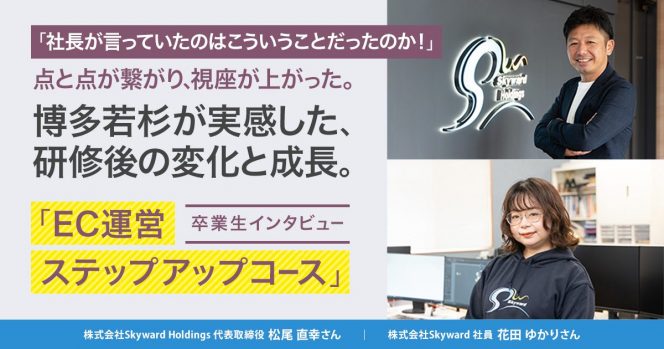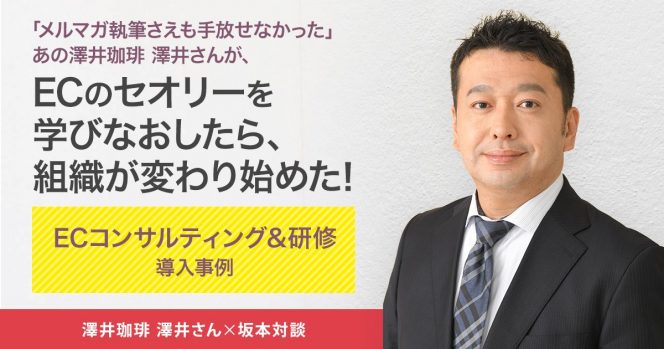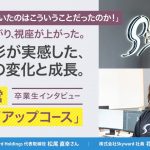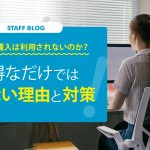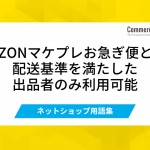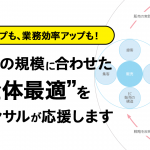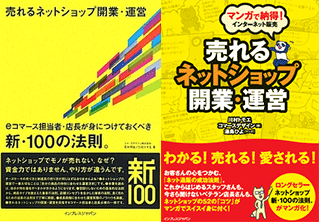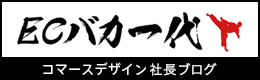今回は、「失敗から学ぶこと」がテーマです。
特に、スタッフが起こしてしまった失敗や社内で起こったトラブルから、「関係者みんなで学び、前向きに受け止め、改善していくためのコミュニケーション」について考えてみようと思います。
「なぜ、悪い展開に行ってしまうのか?」、逆に「よい展開につなげるには、どうすればいいのか?」。スタッフとのコミュニケーションや、チーム作りに悩んでいる方の参考になれば、幸いです。
- 目次 -
コミュニケーションの「悪いパターン」と「よいパターン」
失敗やトラブルが起こったときのコミュニケーションには、「悪いパターン」と「よいパターン」があります。
【悪いパターン】
悪いパターンでよくあるのは、「こんなのだめだ!」と失敗を責めること。失敗した人は反省するけれど、ちょっとしこりが残る感じになります。
【よいパターン】
よいパターンは、まず「何でこういうことが起こったのだろう?」と失敗した人と関係者が一緒に考えることから始めます。
失敗した人は「そうか、自分はこういう風に思っていたけど、実際はこう捉えた方がよかったんだな」と気づき、反省しつつも、失敗から学ぶことができます。
さらに、関係者も含めて「次はどうしたらいいのか?」、「今後の改善のための発見ができた」と前向きに着手することでよい展開へとつながります。
キーワードは、反省よりも「反芻」
では、具体的に例を挙げながら、「悪いパターン」と「よいパターン」の違いを分析してみましょう。下記のケースについて状況を思い浮かべながら、考えてみてください。
例)カスタマー系トラブルがあった場合 お客さんから、問い合わせがありました。 まだクレームまではいかないけれど、不満な雰囲気を漂わせています。 これに対し、カスタマーサポート(CS)の担当者は、何も気にせず、機械的に返事をしてしまいました。 その結果、お客さんを怒らせてしまい、クレームに発展してしまいました。
このあと、社内でどんなコミュニケーションを取ればよいのでしょうか?悪い展開にいくのか、よい展開にいくのか、ポイントはどこにあると思いますか?
キーワードを先に言っておくと、 反省より「反芻(はんすう)」です。
反省も大事ですが、「反省させる」というアプローチは、悪いパターンになりやすいと思います。反省を求める前に、まずはいったん、みんなで噛みしめて反芻することの方が大事です。
正論は、「反省させる」アプローチ
ところで、悪いパターンでいう「反省させる」というのは、どういうことでしょうか?
さきほどのケースを思い出してみましょう。
<前提> お客さんから、不満げな問い合わせがあった。
⇩
<反省させるアプローチ> 「お客さんが言っていることの行間を読めば、不満なことが分かるだろ!」 「そんな機械的な対応してるから、ダメなんだ!」 「お客さんの気持ちになって考えろ!」 「こういう時は相手の気持ちを汲んで対応するんだ。考えれば分かるだろ!」
上記のどれも正論ではあります。間違ったことは言っていないけれど、言われる側の立場に立ってみれば、正論はどうしても「反省させるアプローチ」になってしまいます。
よい展開につなげるためのプロセスとは?
「反省させる」アプローチに対して、「一緒になって考える」とか「反芻する」アプローチは、これからご紹介する形です。 遠回りと思われるかもしれないですけれど、ひとつの考え方だと思って聞いて下さい。
3つのステップを覚えておこう
「よいパターン」には、次の3つのステップがあります。
この3つのステップのことを、「リフレクション」(省察)といいます。
<リフレクションの3ステップ> ステップ①:「事実が何であったか?」「実際、何があったのか?」を振り返る(反芻する) ⇩ ステップ②:事実から「どんなことがいえそうか?」を解釈する ⇩ ステップ③:解釈を踏まえて、「今後どうしていくのか?」を考える
当たり前の話をしているようですが、ポイントは、最初に解釈を入れないで、「事実として何が起こったか?」ということを反芻すること。つまり、 いったん思い出すというアクションが大事です。
多様な解釈が深い結論へ導く
次に、「そこから何がいえそうか?」ということを解釈していくわけです。…が、人によって解釈は違います。 販売の人、CSのメンバーの人、ベテラン、社長さん….。それぞれの立場によって、解釈が変わってくるのです。
実は、この「解釈の多様性」が大事です。多様な解釈から、様々なディスカッション(議論)が起こり、より深い結論へと導いてくれます。
そして、最後に「じゃあ、具体的にどう改善しようか?」という、解決策の話が出てきます。
この段階が、いちばんプラス効果があるありがたい情報です。しかし、ここにたどり着くためには、先の2つのステップ「まず事実をふり返り、そこから多様な解釈をして議論をする」というプロセスが必要です。
失敗から学びを得るには?
それでは、改めて、リフレクション(3つのステップ)を悪いパターンと比べてみましょう。
<悪いパターン> ・「反省しろ!」 ・「こういう時はこういう風にするもんだ」 ・「考えれば分かるだろ」 ・「次から気を付けるんだぞ!」
上記のような対応は間違ってはないのですが、反省を促すだけで、多様な解釈が出てくる余地がありません。反芻の場合は何が変わるのかというと、人によって解釈が変わるわけです。 ここが「失敗から学ぶ」ための重要なポイントです。
言い訳の中にヒントがある
たとえば、失敗の裏に以下のような事情があったとしましょう。
「この時、別のお客さんからクレームが来ていて、電話を待たせていたんです」
「私、〇〇業務で店頭にもう出ないといけなくて、パートの〇〇さんもちょうど帰るところで…。とにかく急いでメール1本だけ返したので、こんな風になってしまいました」
こうした事情を聞かずに、「言い訳を言うな!」と一言で片づけてしまうと、解決のためのヒントがなくなってしまいます。 上司からすると、イラッとするところかもしれないですが、言い訳が混ざることを許容することも大事です。 なぜなら、言い訳についての解釈を話し合っているうちに、新しい気づきが出てくるからです。
・「そういえば、この商品はこういうお問い合わせが多いですよね」 ・「そもそも、この商品どうなんですか?」 ・「予約販売で買った人は、大体トラブルになっていませんか?とすると、予約販売自体どうなのかな?」
念のため言っておきますが、 ここで言いたいことは、予約販売がダメという話ではないですよ。
「CSのメールの返信が悪かった」という一面の裏にある多様な解釈を通して、リフレクションをするうちに、商品自体の問題や売り方の課題など、さらにいろんな解釈が出てくるのです。
リフレクションから、新しい解決策が生まれる
結論としては、失敗の一面だけを見て、反省を促すだけの対応になると、その場はすぐに収まったように見えますが、その裏にある多様な背景が分からないままになります。
例)返品対応のオペレーションが不明確な場合 社員:「確か、社長がこういう場合のルールを最近変えたと思うんですが、新しいルールは文書化されてましたっけ?」 上司:「されてないね」 社員:「これって、どう思います?」 上司:「分からないから、社長に聞いて」 社員:「社長、いないですよ」
例えば、上記のようなやりとりの結果、メールの返信が定型的になってしまった場合、最終的に「トラブルは社長のせい…」みたいな感じになってしまう可能性もあります。
こういったことって、ありがちですよね…。社長でなくとも、担当者しか分からず、「属人化してブラックボックスになっている業務」はリスクが大きいです。ですから、できる所からマニュアルを作っておきましょう。参考記事はこちら。
話を戻すと、何か問題が起こった時に、いろいろな人が、様々な事情を言うことを許すということも、ときに必要です。まどろっこしく感じるかもしれませんが、背景にある多様な事情が分かってきて、問題を根から断つような新しい解決策が見つかる場合もあります。
つまり、急がば回れ効果ですね。失敗から学ぶには、「反省」より「反芻」が大事ということになります。
まとめ
今回は、失敗が起こったときに、「言い訳を許し、みんなで意見を述べ合うことで、根本解決につながるケースもある」ということをお伝えしたくてお話しました。
「常に上の人が正しく、下の人は従う」という昭和風(または江戸風)のマネジメントで育ってきた人は、同じような振る舞いを部下にしてしまう傾向があると思います。 不幸にして、親から厳しく育てられた子どもが大人になると、自然と厳しい子育てをしてしまう話もありますよね。
しかし、時代は変わっていますので、「自分が受けたことを、そのまま下に引き継ぐ」ことを止められるのは、中間世代の方にしかできないことだと思います。「昔はこうだったんだけどなあ」という思いが頭をよぎっても、新しいやり方を試していくことも大切です。
P.S.
何か失敗やトラブルが起こった時は、社内体制や業務を改善するチャンスでもあります。
ただ、「日々のタスクをこなすのに精一杯で、なかなかじっくり考える余裕がない…」という方も多いでしょう。そんなとき、私たちコンサルタントがお力になれるはずです。
今回お話ししたようなマネジメントをはじめ、今の時代に沿った戦略や思考法もご提案できます。ご興味がある方は、ぜひ弊社コンサルティングの案内ページをご覧ください。
この記事を書いた人
-
コマースデザインは、EC事業のコンサルティング会社として、ECのお役立ちツールやECコンサルティングを提供しています。全サービスの累計支援先企業は23,000社を突破しました。「色々な個性を持ったお店が数多くあり、お客さんに豊かな選択肢があるEC業界」を目指し、中小ネットショップ事業者の皆様の「強み」を引き出す支援を行っています。
詳しくは、コマースデザインについてをご覧ください。
記事一覧を見る
 お客様の声2025年3月19日「社長が言っていたのはこういうことだったのか!」点と点が繋がり、視座が上がった。博多若杉が実感した、研修後の変化と成長。| 「EC運営ステップアップコース」卒業生インタビュー
お客様の声2025年3月19日「社長が言っていたのはこういうことだったのか!」点と点が繋がり、視座が上がった。博多若杉が実感した、研修後の変化と成長。| 「EC運営ステップアップコース」卒業生インタビュー 最近のコマースデザイン2024年12月23日2024年のEC業界を総まとめ!1年をふりかえるコンサルタント座談会
最近のコマースデザイン2024年12月23日2024年のEC業界を総まとめ!1年をふりかえるコンサルタント座談会 ネットショップの売上アップ2024年3月18日無意識の思い込みが足かせに!?「成長のリミッター」を外して売上増加につなげるポイント
ネットショップの売上アップ2024年3月18日無意識の思い込みが足かせに!?「成長のリミッター」を外して売上増加につなげるポイント お客様の声2024年3月11日「メルマガ執筆さえも手放せなかった」あの澤井珈琲 澤井さんが、ECコンサル&研修でセオリーを学びなおしたら、組織が変わり始めた!ECコンサル&EC運営ステップアップコース 導入事例インタビュー
お客様の声2024年3月11日「メルマガ執筆さえも手放せなかった」あの澤井珈琲 澤井さんが、ECコンサル&研修でセオリーを学びなおしたら、組織が変わり始めた!ECコンサル&EC運営ステップアップコース 導入事例インタビュー