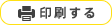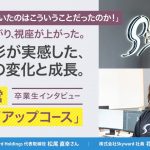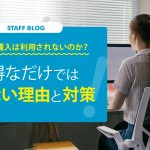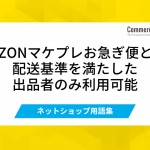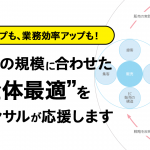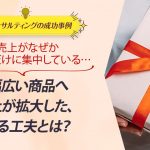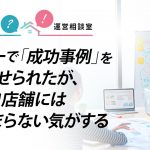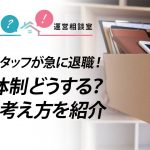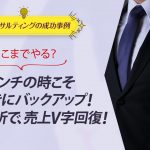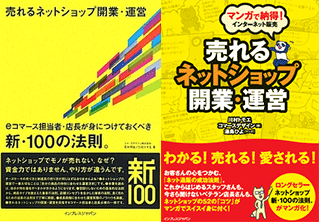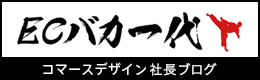こんにちは、コマースデザイン亀田です。
みなさん、仕事で問題が起こったときにどう対処すればいいのか、悩んだ経験はありませんか。実際にコンサルティングのご相談でも、管理職やリーダーの方々から「メンバーが自分で問題解決できるようになってほしい」という声をよく伺います。
そこで今回お話ししたいのが「問題解決の基本」についてです。これをしっかり理解しておくと、部下やメンバーにも効果的に説明しやすくなります。よくある典型的な間違いや、個人と集団(組織)の違い、注意点など、具体例も交えてご説明します。ぜひ参考にしてみてください。
- 目次 -
前提:問題解決とは何か
問題解決とは、文字のとおり問題を解決すること。
当たり前ですよね。でも実は問題解決には、ちょっとしたコツがあるってご存じでしょうか。このコツが職場で共有されているかどうかで、対処方法が大きく変わるんです。
ということで具体的な考え方をお伝えする前に、今回取り上げる「問題解決」とは何なのか、前提として少し深掘りしてお話ししておきたいと思います。
基本を覚えておけば、何にでも応用できる
問題解決は、ネットショップに限らず、どんな分野の仕事にも応用できる考え方です。
たとえば「売上が伸びない」「業務効率が悪い」など、日々の業務にはさまざまな問題が発生しますが、こうした問題はすべて、この記事でお伝えする考え方に沿って整理すれば解決しやすくなります。
もちろん、うまく使えるようになるにはトレーニングが必要です。でも、みなさんがお箸を自然に使いこなしているように、慣れてしまえば自然に活用できるようになります(お箸も最初はトレーニングが必要ですよね)。
焦らず、じっくり身につけていただければと思います。
「個人」と「集団」の2つのパターンがある
上述のとおり問題解決は、どんなケースにも通用します。ただ、以下で整理するとおり、個人と集団では難易度が変わってきます。関わる人数が増えれば、それだけ利害関係が複雑になるからですね。
-
個人の場合
- 日常生活の些細な問題や、一人で取り組むような課題などが該当します。
- 比較的シンプルに原因を特定しやすいのが特徴です。
-
集団の場合
- たとえば「製造担当」「出荷担当」「顧客対応担当」「販売担当」など複数の立場の人が関わると、利害のズレから衝突しやすくなります。
- アプローチを誤ると、責任のなすりつけ合いに発展するリスクも。
ちょっと「集団の問題解決」が難しそうと思ったかもしれません。しかし、基本は同じです。まずは個人のシンプルな問題解決のパターンを押さえ、そこから段階的にレベルアップして、集団の問題解決についても理解を深めていきましょう。
個人の問題解決の場合
ここから本題です。まずは個人の問題解決の例から見ていきましょう。
日常の些細なトラブルから大きな課題まで、いくつかの事例を通して考え方をお伝えします。ひとつひとつの事例に、うまく問題解決するためのヒントが隠れています。事例を読みながら、ぜひご自身でも「自分だったらどうするかな?」と考えてみてください。この章の最後に、個人の問題解決の要点をまとめていますので、復習もしていただけます。
暮らしに学ぶ「立ち止まって考える」重要性
最初は身近な例からです。私はコーヒーが好きで、自宅でコーヒーを淹れるとき「電動コーヒーミル」をよく使います。コーヒー豆の風味が損なわれにくいので重宝しています。。
ところがある日、これが突然動かなくなりました。電池を替えてみても一向に動きません。ですが「故障している」と決めつけて捨てるのは早計だと感じ、パーツや電源の接触箇所などに異常がないか細かくチェックしました。
しかし、やはり結果は問題なし。いよいよ故障かと思いました。…が、最後にふと「本当に新しい電池なのか?」という疑問が浮かびました。そこで充電済みだと思っていた電池を残量計で確認してみたところ、実は充電がゼロ。つまり、電池の充電器側に問題があったんです。あらためて充電がきちんと完了している電池を入れ直すと、無事に動いてくれました。
もしこのプロセスを踏まずに「壊れたから買い換えよう」と早々に処分していたら、せっかく正常な機械を無駄にするところでした。目の前の症状だけで判断せず、一度立ち止まって、なぜ問題が起きているのかの構造を冷静に確認する姿勢が大事、ということが伝わったでしょうか。
スポーツに学ぶ「分解して課題を明確にする」重要性
次はスポーツの例です。サッカー部で、シュートが上達しなくて悩んでいる生徒がいました。そこでコーチは「シュートが入らない理由」を要素分解してみることに。すると、次のような可能性が見えてきました。
- ボールを足のどこに当てるのかやキック力など基礎的な技術が不十分
- 状況判断が苦手で、シュートのタイミングが遅れがち
- 軸足を置く位置が悪く、うまく踏み込めていない
- 体格差があり、対戦相手に当たり負けして軸がブレてしまう
- ゴールキーパーの位置を確認できていない
こうして分解してみると「シュート」1つの中には技術やフィジカル、状況判断など、あらゆる要素が関わっていることがわかります。第三者の意見を聞けば、自分では気づかない原因が見つかることもありますね。
大切なのは、いきなり具体的な対策だけに飛びつかないことです。一度立ち止まって「問題を要素分解する」「周りの意見を聞く」といった初動がポイントといえます。
医師やコンサルタントも同じように問題解決している
医療の世界でも、立ち止まって問題を分解する大切さは共通しています。たとえば患者さんが「熱があるんです」と相談してきた際、すぐに解熱剤だけ出すお医者さんはまずいないですよね。普通は問診・触診・聴診を行い、必要があれば血液検査やレントゲンなども実施して、病気を絞り込んでから薬を処方します。
つまり「熱がある」という症状は、病気を発見するきっかけであって、原因ではないということです。薬で熱を一時的に下げられても、原因の病気が治っていなければ、また症状が出てきてしまいます。
私たちコンサルタントも、医師と同じで、立ち止まって問題を分解すること、そして全体を観察することを大切にしています。たとえば「売上が下がった」という悩みがあったら、「じゃあ広告出しましょう」ではなく次のように状況確認から入るイメージです。
- 売上が下がったのは、いつからか
- 何か思い当たる出来事はあるか
- 競合他社の動向を調べたか
- 検索経由の売上が下がっているなら、どのキーワードの流入が減っているのか
たしかに売上低下に広告は役立ちますが、杓子定規に広告を処方するのでは「とりあえず解熱剤」と変わりません。それはそうですよね。本当の問題の核心は 売上が下がる状態を生んでいる構造にあるのですから、まずはこの構造をしっかり把握して解決しなければ、また同じ問題が再発する可能性が高いです。
したがって、ヒアリングの中で、お店の方自身も気づいていない原因も含めて浮き彫りにするところからはじめるわけです。
つまり「構造(立ち止まって分解)」→「課題」→「対策」の順で考えること。これが大切です。当社のコンサルティングでも徹底している基本の動作です。問題解決の基本として、みなさんもぜひ押さえておいてください。
対策を急がず、構造から全体をとらえる姿勢が大切
整理します。ここまでの事例からわかるように、個人の問題解決で大切なのは、すぐに対策へ飛びつかないことです。症状にばかり気を取られると、背景にある構造を見落としてしまいがちです。
-
構造
- コーヒーミルの動く仕組み
- シュートがうまくいかない体と動きの構造
- 人体が発熱する構造
- コンサルタントが見るネットショップの売上が下がる仕組み
-
課題
- 実は電池が充電できていない
- シュートに必要な基本スキルが足りていない
- 熱以外にも明らかな感染症状がある
- 競合が増え、値段で差をつけられている
-
対策
- 新しい電池を入れる
- まずは基礎体力や動きのクセを修正する
- 根本の病気を治す治療をする
- 競合への対抗策を検討する
問題の核心にある構造をしっかり把握するためにも、いきなり対策を打たず、一度冷静に立ち止まり、問題の構造を見る姿勢を意識してみてください。
集団(組織)の問題解決の場合
ここからは、集団・組織で問題解決をする場合のお話です。
基本のプロセスは個人と同じで、症状が見えたら「構造」→「課題」→「対策」の順で進めます。ただ個人の問題解決に比べると、集団では難易度が2段階ほど上がります。関わる人数が増えるほど全体が見えづらくなるうえに、人間の利害や感情が絡んでくるからですね。
では集団では、「構造」→「課題」→「対策」以外に何が必要になるのでしょうか。これも構造から紐解いていきましょう。
なぜ集団では全体構造が見えづらくなるのか?
たとえば、売上が落ちているネットショップで考えてみましょう。
個人で「売上が落ちた」という問題を解決する場合は、次のような要素を確認して整理していきますよね。
- 具体的にいつから、どのくらい落ちているのか
- 落ちているのはどの商品か
- 競合となる他社はいるのか
- 原材料や仕入れコストに変化はないか
ところが集団になると、ややこしいことになってきます。いろいろな性格や利害を持つ各関係者がそれぞれ違った解釈をするので「この調子だとどんどん落ちていく」「あの施策がよくなかったのでは」など、ただ不安を煽るだけだったり、急な方向転換を図ったりする可能性も。
まして、部署間でお互いを軽んじたり、敵対したりする態度があると、ますます正しい問題構造を把握しづらくなります。「営業が数字に神経をつかっている中で、製造や出荷はルーチン業務で呑気だな」「ページ制作が悪い」といったギスギスした主観のコメントが出てきかねません。当然、組織の人間関係を悪くするだけでなく、全体構造の把握を妨げます。
また、同じ組織でも、部署が異なると視界不良になりがちです。社長も全体を見ているようで細部は見えていないということもありますよね。このように視界が不明瞭というだけでも障害なのですが、他部署を軽く見るような態度をすると余計に問題をややこしくします。
ですから、個々の意見に対して落ち着いて聞いてまわり、事実情報なのか感情的な意見なのかを精査していく必要があります。個々の意見に対して「そう判断する理由は?」「結論づけるにはまだ早いと思うんだけど、具体的に何かあったのかな?」と落ち着いて聞いてまわり、事実情報なのか感情的な意見なのかを丁寧に見極めるイメージです。
日頃から情報共有の習慣をつくり、良い人間関係を育む
では、どのようにすれば、こうしたバラバラな状況を打破できるのか。
キーになるのが、情報や姿勢をみんなが同じように共有することです。
まず情報。集団で問題構造をスムーズに把握するためには、普段からの部署同士での情報共有が欠かせません。たとえば、在庫状況や売上推移、競合動向など、経営にかかわる基本的な数値や指標は、マネージャーだけでなく全メンバーにもある程度はシェアしておくのが理想です。こうすることで、いざという時に詳細調査がしやすくなります。
次に姿勢。人間関係のトラブルを避けるために「誰かを責めるのではなく、課題に目を向ける」といった会社としてのあるべき姿勢を日頃から意識しておいてもらうことも大切です。特に経営者やリーダーは、組織内の雰囲気づくりや心理的安全性の確保に大きく影響を与える存在。イライラや不安を表に出しすぎず、冷静な舵取りを心がけてください。
構造から課題を特定し、複数の対策を分担で実行する
集団で協力して問題の構造を洗い出していくと、さまざまな情報が集まってきます。ドラマでよく見る刑事の捜査会議のように、ホワイトボードやノートなどに相関図を書いて整理していくあれですね。
整理していくと、あやしい容疑者、つまり問題の核心が見えてきます。そして、さらに調査を重ねることで真の課題を見出します。
ここで注意したいのは、やはり言い方や人間関係への配慮です。調べているだけなのに「結局、私のせいにしたいのですね」「何年もこの会社に尽くしてきたのに」など、マイナスな感情を引き起こしてしまうこともあります。感情的になられると、問題解決が進みにくくなるので、情報収集は配慮をしつつ進めるようにしてください。
無事に課題を特定できたら、あとは課題に対して有効な対策を実行していくのみ。以下の例のように、皆で共通認識を持った上で、関係各所がそれぞれ動いていきます。
<課題>
在庫が多すぎて保管場所がない、人手不足で生産がおいつかない
<各担当者がやること>
仕入担当Aさん:材料を仕入れる際に倉庫を確認、在庫管理と連携する
在庫管理Bさん:在庫が消化されていくペースを算出、今後の予測を各部署に報告
生産担当Cさん:在庫管理の予測を参考に、生産ペースを調整、人員を適所に配置
出荷担当Dさん:営業担当に必要数を確認する。在庫管理や生産担当と連携する
営業担当Eさん:在庫状況と生産ペースを把握し、値引き幅について社長決済を仰ぐ
このように同じ目的に向かって、部署の垣根を超えて連携しながら対策を実行していきます。組織の場合は複数の対策を走らせていくことになるので協力的な人間関係がいかに大事か、おわかりいただけるのではないかと思います。
組織全体を考えて行動できるような文化を醸成する
なお、集団で対策を実行するときに障害になりやすいのは、やはり人間の「感情」です。 「自分の立場としては不都合だ」「今までこうだったから変える必要を感じない」といった抵抗にどう対応するかは、管理職やリーダーが頭を悩ませるポイントになります。
結論としては、組織の利益を優先できる人を評価する文化をつくることが大切。
「自分の担当業務だけこなしていればいい」ではなく「自分の業務はきちんとやっているけど、全体はうまくいっているかな?」と配慮し、対話的に全体最適に向けて動く人を評価する。あるいはそういう人を積極的に採用する目利き力も必要かもしれません。
もし、全体最適を考えないメンバーがいる場合は、一度面談をして「それはよくないよ」と指摘するなど、地道なコミュニケーションを取るようにしましょう。こうした調整も、リーダーや管理職に求められる重要な役割といえます。
ポジティブに問題解決するために
今回は「問題解決の基本」についてお伝えしました。長くなったので、最後におさらいをしてまとめます。
この記事で紹介した問題解決の考え方は「売上対策」「業務効率の改善」「組織内の人員配置」など組織の様々な場面に応用できますし、「プライベートで起こる問題」にも活用できます。個人の場合と集団の場合で、難易度の違いや注意点もお伝えしましたが、基本的な考え方は同じです。
<問題解決の心得>
- 問題に対して即対策は、失敗や空回りが起こりやすい。下手な対策だと状況が悪化してしまう可能性があるので要注意
- 状況を冷静に調査するステップバックの姿勢が大切
- 症状が出てきたら、「構造」→「課題」→「対策」の順で対処する
集団の場合は何が難しいかというと、「視界が悪いこと」と「感情が絡むこと」です。
まず、様々な人間が集まる組織は、ただでさえ見通しが悪くなりがちです。視界を少しでもよくして、メンバー全員が会社の目標や課題、組織構造について共通認識をもっておくためにも、日頃から情報共有を心掛けるようにしましょう。
また、問題の背景や構造を調べる際には「相手を否定しない」という態度を徹底する必要があるでしょう。感情的な反発や責任の転嫁は、問題を複雑にするため、課題を見つけづらくなります。そうならないように「組織の心理的安全」は常に担保する。誰かを責めるのではなく、お互いを尊重し合える関係性を育んでいくことは、ポジティブに問題解決をするためにも、また健全な組織を維持し育てていくためにも非常に重要です。
ぜひ、「問題解決の基本」を組織の共通言語としてお役立てください。
P.S)悩んだ際はお気軽にご相談ください
組織が大きくなってくると「基本の徹底」や「情報共有」は難しくなってくるものです。そのため、なかなか思うように問題解決が進まず、孤独を抱えている管理職やリーダーの方もいるかもしれません。
もしどう進めていいか分からない・相談できる相手がいないと感じる方がいらっしゃれば、私たちコマースデザインまでお声がけください。
販促や売上アップの施策に限らず、組織づくりや経営周りのご相談にも1on1で対応しています。興味がある方は、ぜひ、以下のリンク先をご覧ください。お力になれるよう、全力でサポートいたします。
この記事を書いた人
- 大手印刷会社にて人事を経た後、営業として、店頭を中心とした様々な企業の販促支援に従事し、紙から鉄まで多様な企画・制作に携わる。色数や印刷方法など、「成果物の完成度」にズレがちなクライアントの要望をそもそもの目的に合わせ整理し直すなど、「成果とコストの見合った効果的な提案」を得意とする。趣味はサッカー(ポジションはGK)、二児の父。