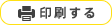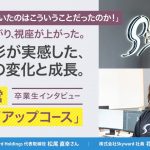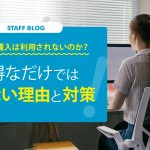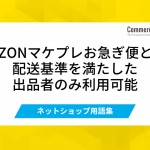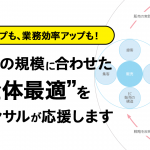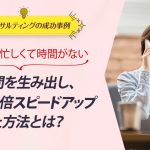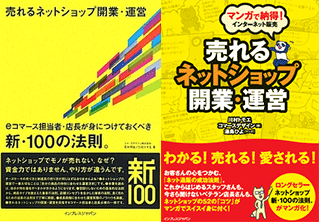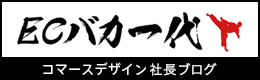こんにちは。コンサルタントの石黒です。
今回はEC事業のマネージャー・リーダー層の方へ向けて「スタッフがきちんと報告してくれない問題」についてお話しします。
チームでEC事業を回していて、以下のような状況に心当たりはありませんか?
- スタッフに仕事を依頼したものの、進捗が見えない
- 経過の連絡がなく、いきなり「終わりました」の報告が来る
- 後から認識ズレが発覚して、二度手間に
仕事を管理しているリーダーとしては困りますよね。しかし、単に注意するだけでは直らず、問題が再発してしまうことも。
ですが、この問題、実は環境を整えることでかなり解消することができます。
この記事では、コミュニケーションのズレが生じてしまう問題の構造をご説明した上で、報告が苦手なスタッフとスムーズに連携するための「報告フローの作り方」についてご紹介します。
具体的な手順もわかりやすく説明していますので、ぜひチームの連携向上にお役立てください。
- 目次 -
なぜ報告しない人がいるのか?典型例に学ぶ対策
まず前提として、「なぜ報告をしない人がいるのか」について考えていきましょう。
報告を「仕事」の一部と認識していない人もいる
チームで働く職場では、報告や相談といった「付随するタスク」も業務範囲に入ると考えるのが一般的です。
たとえば「いつ頃、作業が終わる見込みなのか?」「いまの状況はどうなっているのか?」といった予定や進捗の共有も必要だし、作業途中でイレギュラーなことがあれば相談も欠かせません。
なので「わざわざ聞かなくても状況を報告してくれると思っていたのに…」と期待を裏切られたような気持ちになると、つい相手に非があるように感じてしまいます。
しかし、報告しないスタッフは、意図的に報告していないわけでもないし、困らせようとしているわけでもありません。実は、作業そのものだけが仕事だと認識しているだけ、つまり「チームの常識感覚とのズレ」に起因していることが多いんです。
だから「報告や相談も含めての仕事」と定義しないと、実行してもらえないのです。
「個人競技タイプ」はその傾向が強く出やすい
こうした傾向が出やすいのが「個人競技タイプ」。つまり自分の裁量での仕事や、個人目標に集中する」のが得意な人です。
彼らにとっては、ひとりで仕事をすることこそが常識であり、集団競技では当たり前の「連携」がピンと来ない傾向があるんです。(当社のブログでもたびたび紹介しているサッカー漫画「アオアシ」のアシトくんが最初そうでしたね)

出典:アオアシ(小林有吾/小学館)
もちろん、常識は経験や文化によって異なるものなので、それ自体に「正しさ」や「良し悪し」はありません。しかし、「郷に入りては…」というように、いま所属しているチームとして報告や相談が必要なのであれば、当然、報告や相談を常識に取り入れてもらう必要があります。
そう、この「常識のすり合わせが必要」ということです。
ですから、どうも報告や相談が足りないな…と感じた際は、まず「常識が違うかもしれない」という前提に立つことが大事。
「これぐらい言わなくてもわかるだろう…」「これが常識だろう」と何も言わずに期待するだけでは、すれ違いが起こる可能性があります。社内の常識や相手の常識に頼らず、明確に要件を定義して依頼をするのがはじめの第一歩です。
報告を習慣化するための「報告フロー」の作り方
では具体的に、どのようにすれば、常識が違うメンバーにも報告を習慣化してもらえるのでしょうか。
この章では、報告を習慣として根づかせるための「報告フローの作り方」についてご説明します。
報告の手順には3つステップがありますが、毎回相手に依頼するのも大変ですよね。予めルールを決めて何をどのように報告してもらうのかをきちんと言語化しておくのが継続のコツです。
1. 仕事に着手する前に、共通認識を持つ
ステップ1は、仕事を依頼した直後の報告です。
ここで確認しておきたいのは、仕事を受けた人が 「きちんと着手してくれるのか」「作業内容を正しく把握しているのか」 ということ。仕事の依頼内容について、改めて認識を擦り合わせた上で作業に入ってもらいます。
例えば、報告や相談のルールを決めたり、コミュニケーション時のテンプレートを用意してあげると良いでしょう。具体的には次のとおりです。
- 報告・相談ルールの例
- 仕事内容を確認(復唱)する
- 疑問点があれば、すぐに質問する
- 不明点がなければ、作業終了の目安(予定日)を予告してから作業に入る
- テンプレートの例
- 「〇〇〇〇の仕事、了解しました」
- 「〇〇が分からないので、教えてください」
- 「作業手順は1…2….3……の流れで対応します」
- 「作業完了予定は◯月◯日の予定です」
こうすることで、常識がどうかに関わらず、報告や相談が「仕事」として明確に渡されます。結果として、報告や相談が何もないという状態から脱しやすくなるはずです。
2. 進捗状況を日報で「見える化」する
次にステップ2として、依頼・着手の段階で、作業の経過をいつ・何を・どう報告するのか、明確に示しておくこともおすすめします。具体的な手段としては、日報の活用です。
大前提、経過報告は、大きな仕事を任せるときほど重要ですよね。
いきなり「完成しました!」ではなく、「ここまでで問題ないですか?」と中間の確認ポイントを用意しておくことで管理者も状況を把握しやすくなり、やり直しのリスクも下げられます。
なので、経過報告を簡単にするツールとして「日報(作業報告書)」の導入をおすすめします。日報をルーティーンに取り入れることで進捗共有が簡単になり、作業の「見える化」に役立つはずです。
日報の内容は「今日何をして、どこまで進んだか」をまとめるシンプルな形式で構いません。報告する項目を事前に決めておくことで、管理者から問いかける負担が減り、スタッフも自分の進捗を振り返りやすくなります。
これもルールやテンプレートを用意しておくと良いですね。
- 日報ルールの例
- 仕事をした日は必ず日報を出す
- タイムカードも兼ねているため、作業日と時間を明記する
- 仕事内容と進捗度を記す
- 次の作業予定も書き出す
- 日報テンプレートの例
- ◯月◯日 ◯時〜◯時
- 作業内容:◯◯、◯◯
- 進捗度:◯◯%
- ◯◯作業が遅れたので、明日対応予定
- 明日の作業は◯◯、◯◯
この方法は、稼働時間や作業量を把握しにくい在宅スタッフにも効果的です。日報をタイムカード代わりにすることで、管理コストを下げることができます。
日報の取り入れについては、以下の記事でも詳しく説明しています。あわせてご覧ください。
3. 課題や改善点の記録を蓄積していく
ステップ3は課題や改善点の蓄積。
作業中に何か課題や問題点が出てきた場合も、日報にきちんと記録しておくことで、認識のズレや誤解に素早く対処することができます。それだけではなく、日報は業務改善や社内マニュアルのヒントとして役立てることもできます。
例えば作業途中で、指示されたこと以外の確認事項が出てきた場合、確認したことをメモしておくと、後々同様の作業をする時に「あのときは、こうだったから」と対応がスムーズになります。
ただし、マニュアルに転用するのであれば、個人的な日報だけではなく、社内で共有できるリストにも情報を蓄積し、チーム内で合意をとる仕組みを作っておくと良いですね。
- 改善点の報告・相談ルールの例
- 作業中に指示内容以外の不明点や課題が出てきたら、すぐに確認する
- 依頼者に確認した内容は日報に記す
- 新しく発見したことや注意事項は、別の作業メモ(スプレッドシート)にも記録する
スプレッドシートなどの管理シートは、全体で使うものとして、チームの意見も取り入れながら、テンプレートやフォーマットを整えておくと使い勝手がよくなるのでおすすめですよ。
報告を仕事の一部に組み込んで、組織の生産性を高めよう!
この記事では「スタッフからの報告がなくて、進捗が見えない…」というマネージャー・リーダー層向けに、スタッフが自然に報告できるようになる「報告フローの作り方」をご紹介しました。
ポイントは、「仕事の環境によって、常識が違う」大前提をしっかり理解すること。
これまでまったく異なる環境にいた人に仕事を依頼する際は、依頼している作業だけでなく報告も込みで仕事 であることをわかりやすく伝え、業務に取り入れてもらう仕組みを作るようにしましょう。
フローを作る際は、以下の3ステップを押さえておくと、伝わりやすくなります。
- ステップ1:仕事に着手する前に、作業内容や流れ、完了予定について共通認識を持つ
- ステップ2:仕事の経過や進捗状況を日報で報告する。大きな仕事ほど、進捗の確認は大事
- ステップ3:作業中に発見した課題や改善点はきちんと報告する。情報を蓄積していけるように社内で共有できるリストで管理する
こうしたステップをチームで共有し、運用・改善を繰り返すことで、連携ミスが格段に減り、組織の生産性も上がります。個人戦に慣れたスタッフでも「報告」の大切さがしっかり浸透してくるはずです。
ぜひ取り入れてみてください!
P.S)組織のコミュニケーションの悩みはコマースデザインまで
「報告不足やコミュニケーションの課題を根本から解決したい」「在宅スタッフも含めたフロー構築のノウハウを知りたい」という場合は、ぜひお気軽にコマースデザインへご相談ください。
コンサルタントが1on1でつき、テンプレートの導入やスタッフ教育の具体策など、豊富な実績にもとづくサポートを行います。
また、リーダー自身が「チーム連携が苦手で、ひとりで作業を抱えがち…」とお困りの場合もお力になれます。どうぞご遠慮なくご連絡ください!
以下のリンクよりお気軽にどうぞ!
この記事を書いた人
- エクステリア通販会社にて、店長業務に加えて物流・ユーザサポート・システム開発まで幅広く担当。市場ニーズと競合度を見極めて自社オリジナル商品を企画、自ら販促全般まで行って人気商品を量産。楽天ショップオブザイヤーにてジャンル賞を受賞したが、独自ドメイン店にも明るい。休日はバンド活動中。