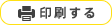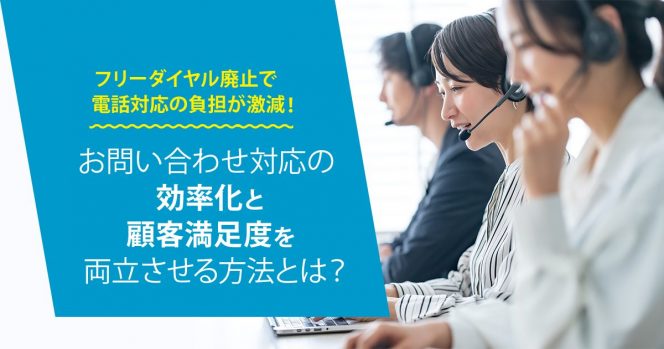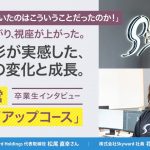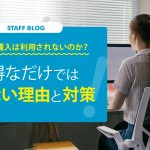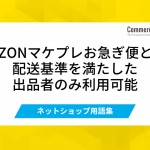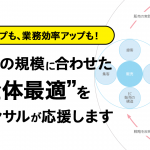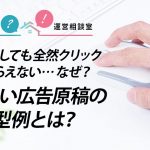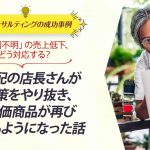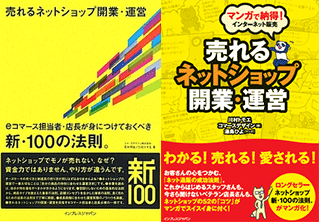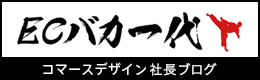こんにちは。コンサルタントの槐(えんじ)です。
今回のテーマは、専門店タイプのネットショップの販促について。
専門店といえば、やはり豊富な品揃えや深い知識が強み。特定のカテゴリに特化しているからこその「ディープな接客」がお客さんを強くひきつけるんですよね。
しかし、日頃ネットショップを巡回していると、せっかくの専門店なのに強みをアピールできず、お客さんを逃してしまっているお店も少なくありません。
そこで今回は、なかなかお客さんが定着せずお困りの専門店へ向けて「お客さんを強力に引き込んで、売上を伸ばすコツ」をご紹介します。
キーワードはズバリ「熱」。
専門店だからこそできる「熱」のこもった訴求によって、お客さんの滞在時間が延び、購入やリピーター獲得に繋がりやすくなるんです。
専門店、ネットショップでは妙におとなしくなる現象
まず前提として、専門店ならではの「熱」の重要性からお話ししていきます。
冒頭でもお伝えしたとおり、専門店の大きな強みは「特化した品揃え」や「商品知識の深さ・豊富さ」にあります。しかし、品揃えと知識さえあれば専門店として成功できるかというと、実はまだ不足があります。
何が足りないのか。それが「熱」です。
アパレルでも家電でも何でも良いのですが、実店舗の接客を思い出してみてください。
- その用途でしたら、こちらの商品の方がおすすめですよ!
- 私もこのアイテム使っていて、あの商品と組みあわせるとスゴいですよ!
このように、お客さんのニーズにあわせて熱心に商品を紹介してくれますよね。お客さんは、この「熱」に圧されて、そのお店や店員さんのことを信頼し、ついいろいろな商品を手に取ってしまいます。(ときには「圧」を感じて引いてしまうこともありますが)
しかし、ネットショップになると、なぜか専門店からこうした「熱」が失われ、淡白な接客にトーンダウンしがちです。
たとえば「こちらもおすすめ」「ご一緒にいかがですか」といった、意図がつかみにくいレコメンドで提案が終わってしまっているケース。心当たりがある方も多いのではないでしょうか。
お客さんの立場になるとわかりますが「こちらもおすすめ」の一言だけでは「なぜ、その商品がおすすめなのか」が伝わってきませんよね…。そこには実店舗のような「熱」はこもっていないので、興味をひきつけられることもほとんどありません。
結果、お客さんは離脱してしまい、せっかくの専門的な品揃えも知識も活かされず…と非常にもったいないことになってしまいます。
- 目次 -
品揃えと知識に「熱」を掛け算し、お客さんを引き込む
では、専門店はどうしたらいいのでしょうか。
もうお察しかと思いますが、品揃えと知識に「熱」を掛け算する必要があるんです。
以下、悪い例と良い例を比べつつ説明します。イメージをつかんでいきましょう。
悪い例:専門性が伝わらず、お店に興味を持ってもらえない
まず悪い例は、上述した、実店舗のような「熱」のある接客が不足している状態。具体的には、その商品に関する詳しい説明こそ書かれているものの、そこからお店なりの専門性や熱が伝わってこないパターンです。
たとえば、元プロ選手が経営するフットサル用品専門店で考えてみます。
フットサルの専門店にくるお客さんの多くは、当然フットサルに興味がある人です。なので「元プロ選手の経験をもとにしたレコメンド」は、非常に強い”引き”になると考えられますよね。
しかし、そうした「元プロ選手らしさ」を出すことなく、上述したように「こちらもおすすめ」「ご一緒にいかがですか」のような熱のこもらない言葉で商品をレコメンドしていたなら、どうなるでしょうか。
おそらく、お店に興味が持てず、よほど必要な商品を探しているのでもない限り「自分の目的に合わないお店だな」と感じ、すぐ離脱してしまいます。
良い例:専門性と熱意が伝わり、お客さんが引き込まれる
では反対に、以下のような熱いレコメンドが行われていたとしたら、どうでしょうか。
当店は元プロ選手の店長が運営するフットサル用品の専門店です!
店長自らが実際に使い倒して「本当におすすめできる」と感じたシューズやウェアだけを厳選して取り揃えています。現役時代の経験をもとに、初心者から上級者まですべての方にピッタリの商品をご提案します!
・当店の紹介はこちら(リンク)
・店長愛用!プロも納得の厳選アイテムはこちら!(リンク)
いろいろな意見はあると思いますが、少なくとも「こちらもおすすめ」の一言よりは何か訴えかけてくるものがあるのではないでしょうか。なかには「このお店なら、自分に必要な商品と出会えそう」「ほかの商品も見てみたい」と思われた方もいるかもしれません。
このように、品揃えと知識に「熱」が掛け算されると、専門店の強みが発揮され、お客さんはググッと引き込まれるようになるんです。
結果、離脱が減って回遊性がアップし、以下のような好循環に入りやすくなります。
- お客さんに「専門店ならではの強み」が自然に伝わる
- お客さんの購買意欲が高まる
- サイトの滞在時間が増え、いろいろなページを見てみてもらえる
- 離脱率が下がり、購入率がアップ。いろいろな商品を買ってもらえる
- お店への信頼感や好感度がアップし、ブランディングやリピート獲得につながる
- ブランディングやリピーター獲得
なお、専門店における熱の重要性については、以下の記事でも詳しく説明しています。あわせてご覧ください。
専門店が「熱」を伝え、お客さんを引き込む4つの方法
品揃えと知識に「熱」を掛け算することの重要性が整理できたところで、ここからは、具体的に「熱」を伝える方法を4つに絞ってご紹介します。
お店のデザインやコンセプトによって「できる・できない」はあると思いますが、以下を取り入れていくことでお客さんの反応も変わってくるはずです。ぜひ検討してみてください。
1. 商品画像で店舗の強みや思いを伝える
お客さんの流入経路は多くの場合、商品ページです(特に楽天などのモール店では顕著ですよね)。
なので、まずは商品ページに載せている「商品画像」で、あなたのお店の強みや思いをお客さんに伝えましょう。
専門店ならではの深い知識や熱を伝えるには文章が最適で、商品画像だけで伝えるのはなかなか難しいのですが、商品を探してザッピングしている段階のお客さんは、説明文はあまり読んではくれません。
そこで、まずはお客さんを文章に引き込むために、商品画像を活用するわけです。
具体的には、以下のような対策を検討しましょう。
- 画像に店舗紹介を含める
- 例:専門店だからこそできるこんなサービス
- 例:専門店だから扱えるこんな商品
- 店舗の強みや思いを写真+テキストでシンプルに記載
- お店の雰囲気やスタッフの写真
- オーナー・店長の紹介
狙いは、商品画像をざっと見ている段階で「ここは専門店なんだ」「すごく詳しい人が運営しているんだ」と理解してもらうことです。そこから「商品ページを読んでみよう」「他の商品やトップページを覗いてみよう」という気持ちを高めることができます。
2. お店や商品をおすすめする理由を「背景」から書く
画像でお客さんの関心を引き込めると、商品ページの説明文を読んでもらえるようになります。
そこで次は、説明文で「当店での買い物」や「関連商品」をおすすめする理由を背景から丁寧に書き、熱を伝えていきます。こうすることで、お客さんの興味が「商品」から「お店」に切り替わり、専門店としてのお店の世界観に引き込みやすくなります。
具体的なアピールのイメージは先ほど紹介したフットサル専門店のとおりですが、ここではもう一例、グルテンフリーの米粉スイーツ専門店の例も紹介します。(モールのルールを考慮し「アレルギー」という言葉は使わないようにしています)
当店は夫婦で運営するグルテンフリーのスイーツ専門店です。
自分たちの子供がグルテン過敏で辛い思いをした経験をもとに、小麦が合わないお子様にも安心して食べていただけるスイーツを1つ1つ手作りで製造・販売しています。同じ悩みを抱える皆さんに喜んでいただける商品をご提案します。
・詳しくは店舗紹介ページをご覧ください(リンク)
・グルテンフリーの誕生日ケーキはこちら(リンク)
ただ単に「こちらもおすすめ」と言われるよりもずっとお店の熱を感じられますよね。リンクをクリックしたい気持ちも高まるはずです。
3.トップページで専門性をわかりやすく伝える
お店に興味を持ってもらえると、多くのお客さんはトップページを見にきてくれます。(スマホのネットショッピングでは、トップページが回遊の起点になる傾向があります)。
しかし、トップページにも専門性を感じられる情報がなければ「あれ、商品ページで感じた印象と違う」とお客さんは違和感をおぼえ、離脱してしまいます。
ですので、トップページでも専門性を伝えるため、以下のような施策を取り入れておきましょう。こうすることで、トップページに来たお客さんが「なるほど、このお店は専門店としてこのジャンルにとても詳しいんだ!」と感じ、さらにお店への興味を深めてくれます。
-
ファーストビューで専門性を明示
- 例:看板画像で「元プロ選手がいるXX専門店」と伝える
- 例:スライドバナーで店舗紹介ページに誘導
-
取り扱う商品やカテゴリを見せる
- 例:カテゴリナビで具体的なラインナップを見せる
- 例:スライドバナーでセレクト性の高い特集ページに誘導
ポイントはファーストビュー(ページを開いて一番最初に表示される箇所)に記載することです。
ページの中ごろに埋め込むと、情報が埋もれてしまってなかなか見てもらえない恐れがありますので、ファーストビューに入る「看板画像」や「スライドバナー」などを有効活用して専門性をアピールしましょう。
4.店舗紹介ページで持てる熱をすべて伝えきる
最後におすすめするのが、店舗紹介ページの準備です。
店舗紹介ページとは、お店のコンセプトや強み、思いのほか、スタッフ紹介や成り立ち紹介を行うページのこと。義務で設置する「運営者情報」よりも、より深く踏み込んでお店について説明する場所です。
この店舗紹介ページは、専門店にとって非常に大切。なぜなら、このページを見にくるのは「お店に興味を持ってくれた人」、つまり購買意欲が比較的高い人だからです。
商品ページやトップページでは語りきれない熱い思いを、購買意欲の高い人にすべて伝え切ることで、お店への興味や関心が醸成され「このお店で買いたい」という信頼獲得につながっていきます。
たとえば、先ほど紹介したグルテンフリーの米粉スイーツ専門店の場合であれば、次のようなストーリーを語ります。先ほどの商品ページの引き込み文章よりも、長く・深く語るのがポイントです。
実は、私たち夫婦の子どもは小さい頃からグルテン過敏でした。ある日、「どうして僕は誕生日ケーキを食べられないの?」と子どもに言われたことが、このショップの始まりです。
「みんなで同じケーキを食べてお祝いしたい!」そんな思いで試行錯誤をしていく中で、米粉やグルテンフリーの商品に出会ったんです。 自分の子どもや家族はもちろん、同じ悩みを持つご家族や、アレルギーがない人と同じ食生活を送りたいと考える大人の方々にも食を楽しんでいただきたくて、グルテンフリースイーツの専門店を立ち上げました。
ブログやメルマガでもグルテンフリースイーツのお話や、グルテンフリー生活を送るコツなどをお届けしています。
こうしたストーリーは、同じ境遇の人にとって共感できる要素が詰まっており「このお店で買いたい」「メルマガも登録しておこうかな」とお客さんの興味を引く強い力があります。
また、少し脇道にそれますが、メディアからの注目度も高まる可能性があります。最近はテレビ番組や雑誌でも、ネット検索で取材対象を探すケースが増えています。その際に、店舗紹介ページで専門店としての強みがきちんとアピールされていると、メディア露出のチャンスが舞い込むこともあるのです。
店舗紹介ページは、決して多くの人が見に来るページではありませんが、このようにいろいろな人と深く繋がれる効果があります。専門店の活路にもなりますので、ぜひ取り入れてみてください。
専門店ならではの熱でお客さんを引き込もう
以上、専門店だからこそ「熱」を持って、商品や店舗自身の強みを打ち出すことが大切、というお話でした。
具体的に取り組むべきことを整理すると以下のとおりです。
- 商品画像で店舗の強みや思いを伝える
- お店や商品をおすすめする理由を「背景」から書く
- トップページで専門性をわかりやすく伝える
- 店舗紹介ページで持てる熱をすべて伝えきる
どれもちょっとした施策ですが、こうして改善を積み重ねていくと「専門店らしい世界観」が整いはじめ、検索エンジンやSNSを含め、さまざまな入り口からお客さんが買い物をしにきてくれる繁盛店に近づいていけるはずです。
専門店の皆さんは、ぜひ参考に、ご自身のサイトを見直してみてください。
P.S)コマースデザインにご相談ください
「もっと具体的な方法を知りたい」「うちの店舗でも実践できるかな?」と感じたら、ぜひ当社コマースデザインまでお気軽にご相談ください。
商品ページの導線設計から、店舗紹介ページに何を載せるかの検討まで、あなたのネットショップの強みを最大限に引き出す支援をいたします。
みなさんのお店がさらに魅力的に、そして多くの方に深く愛され、購入されるショップになるよう、全力でサポートいたしますので、以下のリンクよりお気軽にどうぞ。
この記事を書いた人

- 槐と書いて「えんじ」。埼玉出身。10年以上EC業界に在籍し、アパレル/美容雑貨/ベビー用品など様々なジャンルを経験。某モールで講師も担当。店の個性を活かした支援、人が育つ環境づくりに興味を持ち、コマースデザインに入社した。中小ECの可能性を信じている。カメラ好きでcanon60D愛用中。スパイスカレーに目がない。